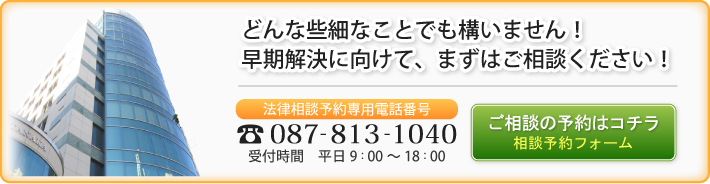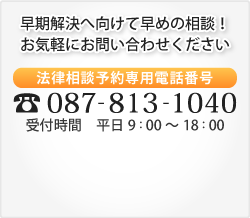相続放棄の申述
例えば、父が死亡し、父に莫大な借金があって、借金を相続したくないといったときには、子は家庭裁判所で相続放棄の申述受理の申立てができます。
この相続放棄の申述受理申立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続をとる必要があります。(熟慮期間といいます。)
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始原因及び自己が相続人になったことを知った時と解され、通常、被相続人が死亡したときからとなることが多いでしょうが、例えば、被相続人と長年交流がなく、被相続人死亡の事実をずっと知らなかったなどの場合には、実際に被相続人が死亡したことを知った日が熟慮期間の起算点となります。
もっとも、被相続人の死亡そのものを知っていたとしても、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情があって、被相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきとされています。(最判昭和59.4.27民集38巻6号698頁)
熟慮期間の伸長
相続放棄については3か月の熟慮期間が設定されていますが、この3か月という期間は意外と短く、例えば、相続放棄の判断をするにあたって、被相続人に債務があるかどうか調査しなくてはならないときには、3か月では足りないこともあります。
そういったときは、熟慮期間の伸長を認める制度も用意されています。(民法915条1項但し書き)
被相続人に借金があるけれども、その金額がわからない、調査に時間がかかる等といった場合には、熟慮期間の伸長も視野に入れつつ、相続放棄申述をするかどうか検討するとよいでしょう。
相続放棄の申述と民事効
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された場合に、被相続人の債務から確定的に免れることができるわけではないことには注意が必要です。
すなわち、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理することは、相続人から相続放棄の申述があったことを公証するにすぎず、民事上、債権債務関係の承継や存否を確定するわけではないのです。
したがって、例えば、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後、被相続人の債権者から相続人に対して訴訟提起があった場合に、これを無視していると欠席裁判となって敗訴し、債務の支払い義務が認められてしまいます。また、裁判に出席して相続放棄の申述の受理があったことを主張しても、相続放棄の効果が認められないと判断されることはあり得ます。
とはいえ、「被相続人が死亡してから」3か月以内に相続放棄の申述受理がなされている場合等、相続放棄の有効性を争いようがないようなケースでは民事訴訟で相続放棄の効果が認められないと判断されることはありません。そもそも債権者が訴訟提起してくることもまずないでしょう。
問題は、相続人が死亡してから3か月を経過しているものの、相続の開始を知ったときから3か月以内である、さらには、最高裁の判例で示されている「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合」であるとして、熟慮期間の起算点を後にした場合は、家庭裁判所での相続放棄申述受理が実務上比較的緩やかに認められていることともあいまって、家庭裁判所での判断と民事訴訟での判断が異なることはあり得ます。
インターネット上には「相続放棄の手続を行います」「全国対応」などとして集客しているサイトが溢れていますが、その中で、このあたりのところをきちんと解説しているものは見当たりません。
相続放棄の申述はそれ自体難しい手続ではないので、「被相続人が死亡してから」3か月以内に手続が行われるような明らかに問題がないケースは、(少し大変だとは思いますが)自分で手続を行うのがコストを考えるとよいと思います。
しかし、やや問題があると考えられるケースは、家庭裁判所での相続放棄の申述受理後のことも考えて、しかるべき対応が可能な弁護士に依頼するのがよいと思います。
遺留分減殺請求の概要
被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人は、一定割合の承継が保障されており、これを遺留分といいます。
遺留分制度の趣旨は、遺産形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の清算にあるなどといわれています。(かかる趣旨に対しては近時批判もあります。)
そして、被相続人が遺留分を超えて贈与や遺贈を行ったために遺留分が侵害された場合にはその処分行為の効力を失わせることができ、これを遺留分の減殺といい、遺留分減殺を内容とする相続人の権利を遺留分減殺請求権といいいます。
以下、遺留分についてごく簡単に説明しますが、実際に遺留分の判定、行使をするにあたっては、細かい具体的事情や諸判例を考慮する必要があるので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
誰が遺留分権利者なのか
相続人となる被相続人の配偶者、子、直系尊属(父、母等)、子の代襲相続人が遺留分権利者です。兄弟姉妹は遺留分権利者とはなりません。
相続権のない者についても遺留分はありません。例えば、子がいる場合の父母は遺留分はありません。
遺留分額の割合はどれくらいなのか
直系尊属のみが相続人の場合・・・財産の3分の1
それ以外の場合・・・・・・・・・財産の2分の1
例えば、相続人として、配偶者、子2人がいる場合には、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各8分の1となります。
遺留分算定の基礎となる財産は何か
●相続開始時の積極財産(債務は控除)
●相続開始前の1年間にされた贈与
●遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与
●不相当な対価でなされた有償処分
●特別受益としての贈与(1年を超えるか否かにかかわらず)
例えば、相続人として子A、Bがいて、Aに遺産(600万円)を全部取得させる旨の遺言がされており、かつ、Aが相続開始5年前に被相続人から贈与として1000万円を受け取っていた場合、Bには400万円の遺留分があります。((600万円+1000万円)×1/2×1/2)
遺言書の種類
自分の生前には仲のよい家族であっても、自分の死後もそうであるとは限りません。相続の問題で関係がこじれ、何十年と争いをしている方々もいます。そのようなことにならないように遺言書を作成しておくことが適切です。
遺言書には、すべて自分が自筆で記載して署名押印して作成する自筆証書遺言と、公証人役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言、遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を封じて、封じられたまま公証人によって公証される秘密証書遺言があります。(その他、特別方式の遺言というものがありますが、ほとんど利用されていないので、ここでは触れません。)
これらのうち、実務上よく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言書の内容については、弁護士などの専門家が関与して、遺言者の希望をお聞きしたうえで、後々トラブルにならないように法的観点から内容を精査するのがよいでしょう。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言をいいます。
全文を遺言者が自筆で作成する必要があり、コピーやワープロ打ちでは不可です。押印や日付を欠いても無効になりますし、修正の場合には所定の方法で修正する必要があります。
自筆証書遺言は公正証書遺言とは異なり、遺言書作成手続が面倒ではなく、遺言書作成そのものの費用はかからない点でメリットがあります。
他方で、自筆証書遺言は厳格に要件が定められており、方式不備で無効になるケースもままあります。
こういった方式不備で無効になることを防ぐため、弁護士などの専門家の関与を求めつつ、遺言書を作成することが適切であるといえるでしょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言をいいます。
公正証書遺言は公証人が関与するため方式不備による無効を回避できますし、遺言書が公証人役場で保管されるため、改ざんのおそれがない点でメリットがあるといえます。
他方で、公証人の立会い、証人が必要であるなど簡単に作成するわけにはいかず、また、別途公証人に支払う費用が必要になる点などがデメリットであるといえるでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人間で遺産の分割方法について話し合うことです。遺言書が存在しない場合、遺産を分けるためには遺産分割協議が必要です。遺産分割協議には相続人の全員が参加しなければならず、一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効です。
誰が相続人となるか、法的にはどれだけの取得分があるかを認識したうえで話し合いを協議を行うことが妥当です。
誰が相続人になるのか
● 子がいる場合は子が相続人となる。
● 子が死亡しており、その子がいる場合はその子が相続人となる。
(代襲相続といいます。この場合の代襲相続は孫、ひ孫へと続きます。)
● 子やその代襲相続人等がいない場合は親が相続人となる。
親がいなくて祖父母がいるときは祖父母が相続人となる。
● 上記による相続人が誰もいない場合は兄弟姉妹が相続人となる。
兄弟姉妹が死亡しており、その子がいる場合はその子が相続人となる。
● 配偶者は常に相続人となる。
誰がどれだけ遺産を取得するのか
誰がどれだけ遺産を取得するかについて、当該相続人が納得する限りは合意で自由に決めて構いませんが、相続分については一応民法に規定があります。
● 子と配偶者が相続人のときは、各2分の1
● 直系尊属(親等)と配偶者が相続人のときは、直系尊属は3分の1、配偶者は3分の2
● 兄弟姉妹と配偶者が相続人のときは、兄弟姉妹は4分の1、配偶者は4分の3
なお、法的な遺産の取得分を判断するにあたっては、特別受益や寄与分等のさらに細かい事情を考慮する必要があります。詳細は一度専門家に相談することをお勧めします。